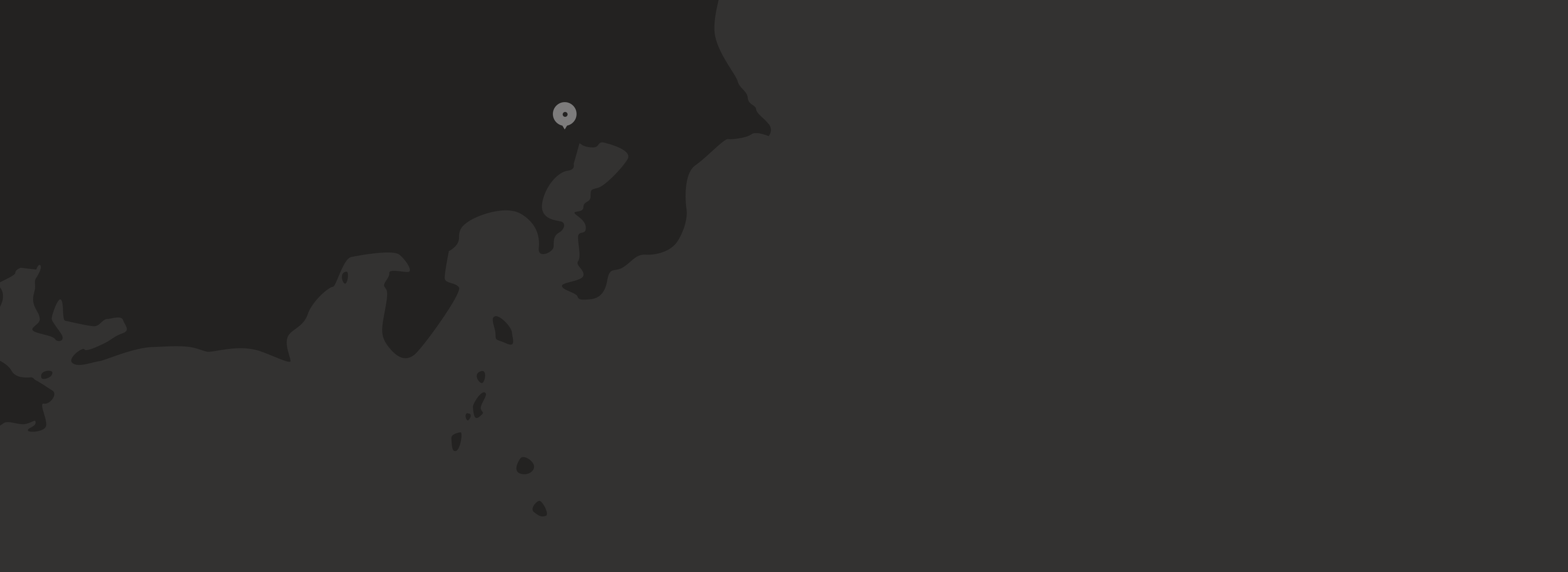Book Nowvacants
Cliquez ici pour confirmer, modifier ou annuler votre réservation.
Plan avec billet d'avion
Plan d'hébergement Shinkansen
Réservation exclusivement pour les sociétés affiliées
2025.04.01
Magasin de chaussures Yamatoya : perpétuer la culture de la chaussure et l'artisanat japonais

À environ 15 minutes à pied de HOTEL RESOL STAY AKIHABARA. En descendant la rue principale de Jimbocho bordée de rangées de livres d'occasion, vous verrez un grand panneau en bois avec le nom « Yamatoya » écrit dessus.
Yamatoya Footwear Store est un magasin de geta (sabots en bois) avec plus de 100 ans d'histoire. Il s'agit d'un magasin bien établi qui livre soigneusement des geta de haute qualité au même endroit depuis son ouverture et qui n'est connu que de ceux qui le connaissent.
140 ans depuis notre fondation, toujours au même endroit

À l'intérieur du magasin
Le magasin de chaussures Yamatoya (ci-après dénommé Yamatoya) a été fondé en 1884 (Meiji 17). On dit que le magasin a été fondé lorsque le premier propriétaire, qui avait suivi une formation de fabricant de sandales à Tokyo, a décidé de devenir indépendant et d'ouvrir une boutique à Jimbocho, suite à un lien familial. Depuis 140 ans, cette boutique se trouve au même endroit que la boutique locale de geta, témoin des changements à Jimbocho.
Un tournant majeur pour Yamatoya a été la rénovation du magasin il y a quatre ans. Même avant la rénovation, le propriétaire et d'autres personnes du magasin discutaient depuis de nombreuses années de la manière de préserver Yamatoya pour l'avenir. La raison pour laquelle cette idée s'est transformée en projet de rénovation était en grande partie due à la présence de Funabiki Ryuhei.
Alors qu'il construisait sa carrière en tant que salarié dans une grande entreprise, Funabiki a commencé à travailler chez Yamatoya après avoir épousé sa partenaire. Voyant les gens de Yamatoya chercher des moyens de transformer leurs rêves en réalité, Funabiki a décidé d'aider au projet de rénovation, pensant qu'il pourrait peut-être mettre son expérience à profit. Avec l'arrivée de Funabiki-san comme nouvelle force, le projet de rénovation de Yamatoya a commencé à avancer avec un grand élan.
Transformation d'une « boutique geta de ville » en un « magasin qui perpétue la culture japonaise »

Espace galerie à l'intérieur de Yamatoya
Alors que les temps changent, quel genre d’endroit souhaitez-vous que Yamatoya continue d’être ? Cette question a été un thème majeur tout au long du projet de rénovation. Funabiki a écouté attentivement les personnes impliquées avec Yamatoya, tant passées qu'actuelles, et a progressivement mis en mots ses réponses aux questions.
« Le propriétaire actuel, de la troisième génération, a déclaré : « Je veux préserver Yamatoya en tant que véritable fabricant de geta », et son fils, de la quatrième génération, a déclaré : « Je veux préserver Yamatoya en tant qu'élément du paysage de la ville et en faire une occasion d'en apprendre davantage sur Jimbocho. » La famille, qui pratique la teinture au pochoir, a déclaré : « Je serais ravie que la boutique contribue à préserver les trésors du Japon. » Nous avons donc cherché des points communs entre leurs histoires. C'est ainsi que nous avons trouvé le concept d'une « boutique porteuse de culture ».
D'un « magasin de geta de ville » qui livre des geta aux habitants, à un « magasin qui perpétue la culture » qui propose la culture japonaise. Une fois le concept décidé, toutes les personnes impliquées chez Yamatoya avaient un objectif clair en tête, ce qui a conduit à des changements dans le magasin.
Par exemple, la moitié du magasin sera transformée en galerie d’art pour présenter les artistes et la culture japonais. Nous avons créé un espace où vous pourrez découvrir la culture japonaise au-delà des simples chaussures. De plus, Yamatoya achète des geta et des tongs directement auprès d'artisans de confiance et travaille avec eux pour créer des produits originaux.
Profitant des atouts d'un magasin spécialisé dans les chaussures qui peut insérer les sangles et les bases des geta en magasin (en insérant les sangles dans des trous de la base des geta pour les attacher), les clients sont en mesure de personnaliser librement les bases et les sangles de leurs geta et de créer leurs propres geta originales.
Nous ne voulons pas seulement être un lieu de livraison de chaussures, mais utiliser les chaussures et notre magasin comme un moyen d'hériter de la culture japonaise et de la connecter à de nombreuses personnes. Dans cet esprit, Yamatoya a été relancé en mai 2021.
Des liens approfondis et élargis grâce au renouvellement

Bases de sandales Geta vendues chez Yamatoya Footwear Store. Chacun a un grain et une texture différents, vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à votre goût.
Funabiki dit qu'il a également ressenti de la pression à mesure que le projet de rénovation progressait.
Yamatoya a 140 ans d'histoire au même endroit. À chaque fête locale, les habitants viennent à Yamatoya et commencent à boire dans la boutique ; c'est un lieu profondément ancré dans la ville. Je ne savais donc pas si les habitants et les habitués souhaitaient voir des changements à Yamatoya, et je m'inquiétais de leur réaction.
Mais le jour de la réouverture, il y avait un flux constant de clients toute la journée. En voyant arriver autant de clients, nouveaux venus comme fidèles, j'ai compris que nos préparatifs n'étaient pas une erreur, et j'étais vraiment content. "
À partir du jour de la réouverture, Yamatoya continuera d'élargir ses liens avec de nouveaux clients à travers des expositions et des événements dans l'espace galerie. Récemment, nous avons même eu des clients venant de l'étranger spécifiquement à Yamatoya.
De plus, un client régulier a déclaré : « Je suis heureux d'avoir plus de raisons de venir à Yamatoya parce que je peux rencontrer divers artistes à la galerie », et il semble que le nombre de fois où les clients réguliers viennent à Yamatoya ait augmenté.
« Le point faible des boutiques de geta réside peut-être dans la petite taille du secteur, mais notre force réside dans les liens étroits que nous entretenons avec nos clients. Le bouche-à-oreille s'est rapidement répandu, et je pense que ces dernières années, nos clients ont attiré d'autres clients », explique Funabiki. La transformation de Yamatoya a permis de rencontrer de nouvelles personnes et d’approfondir les liens avec ceux qui nous ont soutenus jusqu’à présent.
Un lieu comme une passerelle pour connecter la culture japonaise

Tout le monde chez Yamatoya Footwear Store. La deuxième personne à partir de la gauche est Ryuhei Funabiki.
Yamatoya fêtera ses quatre ans de rénovation en mai 2025. Lorsqu'on lui a demandé quel genre d'endroit il aimerait que Yamatoya devienne à l'avenir, Funabiki a répondu : « Je veux que ce soit un lieu qui serve de passerelle pour que les gens découvrent les geta et la culture japonaise. »
Honnêtement, je trouve que les boutiques de geta sont intimidantes et difficiles d'accès. C'est pourquoi je souhaite que Yamatoya soit une boutique accessible à tous. À l'avenir, je souhaite que Yamatoya soit un lieu qui permette aux gens de découvrir le charme profond de la culture japonaise et des geta.
Lorsque vous entendez les mots « geta » ou « culture japonaise », certaines personnes peuvent se sentir intimidées, car ils peuvent sembler très éloignés de leur propre vie. Cependant, une fois que vous franchissez le rideau de Yamatoya, vous réalisez que les geta sont des chaussures décontractées enracinées dans l'environnement japonais et étroitement liées à notre vie quotidienne.
Aujourd’hui, Yamatoya continue d’être une opportunité de nous connecter à la culture profondément enracinée dans la vie japonaise dans les rues de Jimbocho.
Magasin de chaussures Yamatoya
Adresse : 1F Sunlight Building, 3-2-1 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo
HP: https://geta-yamatoya.com/about/
Réseaux sociaux: https://www.instagram.com/geta_yamatoya/
* Pour plus de détails sur les heures d'ouverture et les jours de fermeture, veuillez consulter le lien ci-dessus.