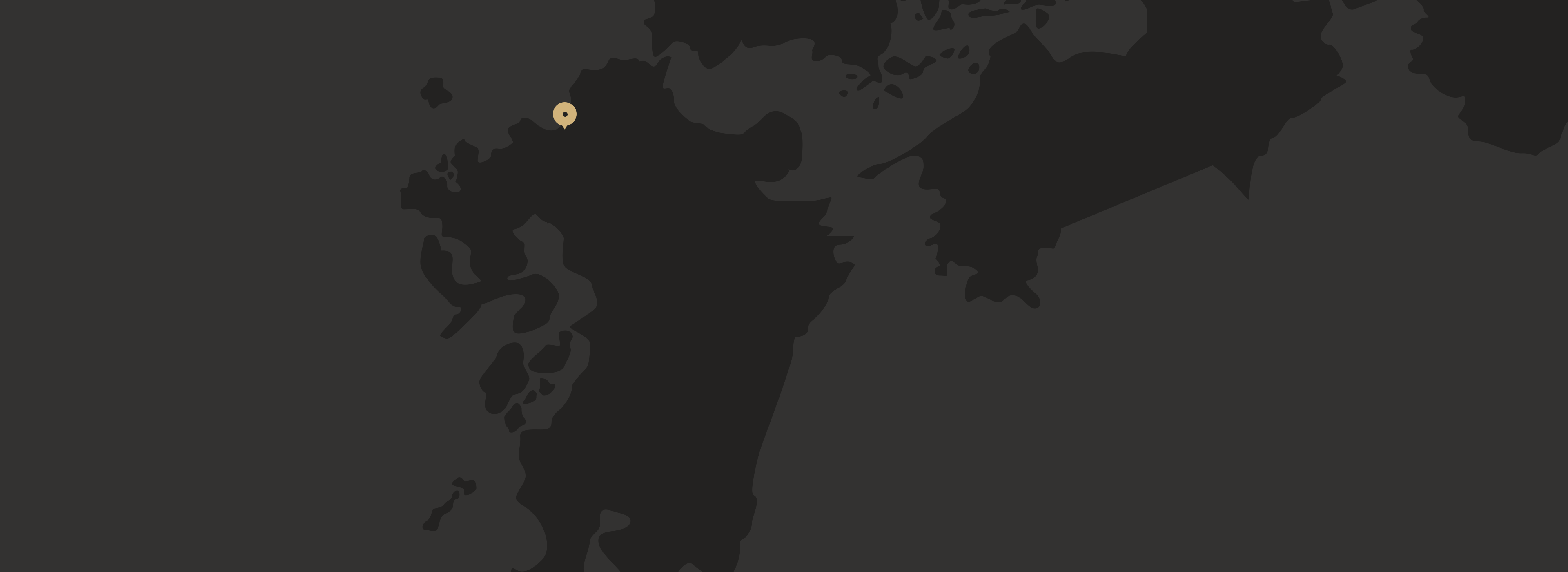Book Nowvacants
Cliquez ici pour confirmer, modifier ou annuler votre réservation.
Plan avec billet d'avion
Réservation exclusivement pour les sociétés affiliées
2025.07.10
Les personnes qui dirigent le Yamakasa et le tissent : Les successeurs de l'histoire et des traditions du Hakata Gion Yamakasa
ÉVÉNEMENTS

Alors que les cris de « Oi ssa, oi ssa » sont portés par le vent, l'été à Hakata commence à bouger.
La voix s'éteint puis revient, provoquant un battement au plus profond de ma poitrine.
La saison des Yamakasa de Hakata Gion bat son plein, depuis le dévoilement des chars décorés de Yamakasa le 1er juillet jusqu'au festival Oi Yamakasa le 15.
Et il y a toujours la présence de « personnes invisibles » au plus profond de ces voix.
Les organisateurs du Yamakasa ne se limitent pas à ceux qui le portent avec ardeur le dernier jour. Ce sont ceux qui préparent discrètement, à l'insu de tous, et qui continuent de soutenir le festival en coulisses qui constituent le Hakata Gion Yamakasa.
Comme si je récupérais les souvenirs de personnes sans nom, un par un.
Cette année encore, les défilés Yamakasa parcourront les rues de Hakata.
Le lien qui est Nakasu, tissé par cinq villes

Photo de groupe de l'année précédente, lorsque Nakasu 5-chome était la zone désignée
La ville de Nakasu ne se réunit pas seulement pour le festival annuel. Nakasu Nagare est composée de cinq villages, de 1 à 5 chome, et chaque village est impliqué dans diverses cérémonies et événements religieux tout au long de l'année.
Parmi les participants figurent non seulement les habitants de Nakasu, mais aussi les commerçants, les employés, les clients réguliers et les connaissances qui fréquentent régulièrement les magasins. Ces personnes, liées par le « destin », soutiennent discrètement la ville.
Un sentiment de solidarité se développe quotidiennement dans toute la ville, et ces liens deviennent encore plus forts à l'approche du Yamakasa.
Les longs manteaux happi, portés par toute la ville, sont identiques, avec le mot « Nakasu » teinté au dos. Ce vêtement est imprégné du désir d'unifier le flux, transcendant les appartenances.
Les personnes impliquées dans le Yamakasa ne sont pas les seules à soutenir le style Nakasu. Avec l'Association municipale de Nakasu comme base, des organisations locales telles que l'Association de prévention de la criminalité, l'Association d'assainissement de l'environnement et l'Association du tourisme de Nakasu sont profondément ancrées dans la vie de Nakasu tout au long de l'année. Le festival et la vie quotidienne sont étroitement liés, des nettoyages locaux et des exercices de prévention des catastrophes aux événements tels que le Festival de Nakasu et le Nakasu Jazz.
« Le festival n'est pas la seule particularité, mais nos contributions quotidiennes à la communauté sont également liées au festival », explique Toshihiko Muraishi, responsable des affaires générales de la deuxième édition du Yamakasa Nakasu Nagare. Membre du Nakasu 5-chome, il est impliqué à Yamakasa depuis plus de 20 ans et travaille au sein de la communauté.
Tomber amoureux de l'Oi Yamakasa - une connexion qui a conduit à une nouvelle vie

Le spectacle impressionnant du festival Oi Yamakasa
Durant ses études universitaires, Muraishi travaillait à temps partiel dans un restaurant-bar de Nakasu. Sur le chemin du retour, il a assisté par hasard au défilé du festival Oi Yamakasa, qui a marqué un tournant dans sa vie.
« J'ai été immédiatement captivé par sa puissance. Je me suis naturellement dit : "Je veux être à l'intérieur de ce bâtiment un jour." »
Quelques années plus tard, il a rencontré quelqu'un qui participait au Nakasu 5-chome, et sa vie à Yamakasa a commencé.
Aujourd'hui membre de l'Association de prévention de la criminalité de Nakasu, il participe aux activités de prévention à Nakasu et, cette année, il est responsable de la ville de Yamakasa tout au long de l'année. Ce rôle implique un travail considérable, de la préparation à l'événement lui-même, et la coordination et la planification en coulisses contribuent au bon déroulement de la Yamakasa. C'est un rôle qui implique de nombreuses responsabilités et qui n'est certes pas facile, mais qui n'en est que plus enrichissant.
En juin, toutes les écoles emménagent dans leurs cabanes et commencent les préparatifs à grande échelle. On dit que chaque école a ses propres coutumes.
Nakasu est un paroissien du sanctuaire de Sumiyoshi. Après la cérémonie d'inauguration, nous nous rendrons également au sanctuaire de Sumiyoshi pour prier. Nous prierons tous pour que le festival se déroule en toute sécurité, sans accident ni blessure.
Yamakasa rassemble une grande diversité de personnes. Des enfants aux personnes âgées, des personnes de tous âges, issues de professions très diverses, comme des chefs d'entreprise et des médecins, peuvent y participer. C'est ce qui rend Yamakasa si intéressant. C'est un espace où chacun peut être soi-même différemment, et où chacun vit l'expérience d'évoluer côte à côte.
« Ce qui compte, en fin de compte, ce sont les relations entre les gens. Être connecté à Nakasu crée naturellement des liens avec les gens ; c'est ce genre de ville. C'est pourquoi je veux perpétuer cette histoire et cette culture traditionnelle. »
Un paysage urbain qui reflète la gaieté et les souvenirs

Vous pouvez voir les chars décorés à côté du bâtiment HOTEL RESOL TRINITY HAKATA.
Le 1er juillet, les chars décorés de Yamakasa font leur apparition majestueuse au cœur de Nakasu. Aujourd'hui, seules quelques rivières en sont dotées, ce qui rend ce spectacle rarissime. Dressés fièrement dans le plus grand quartier de divertissement de l'ouest du Japon, ils dégagent une fierté digne au milieu de l'agitation, décorant la ville comme un tableau sur un paravent.

Sous la direction des principaux fabricants de poupées de Hakata, Mizoguchi Touyou et Nakamura Hiromine, les deux côtés du char décoré prennent progressivement forme.

Le processus d’installation de chaque décoration à la main prend jusqu’à trois jours.

Les chars sont également en cours de construction en même temps.
Comme les chars décorés et portés sont démontés une fois le festival terminé, rares sont les endroits où l'on peut apprécier leur charme tout au long de l'année. Parmi les rares endroits où l'on peut admirer ces chars, on trouve le sanctuaire Kushida, la place Kawabata Zenzai et Hakuhaku, ville profondément liée au Nakasu Nagare.

Les chars exposés à Hakuhaku peuvent être vus toute l'année.
« Hakuhaku » est un musée consacré à la gastronomie et à la culture de Hakata, créé par « Aji no Mentaiko Fukuya », qui œuvre activement au Nakasu Ryu depuis sa création. Situé à côté de l'usine de mentaiko, le musée propose des expositions retraçant l'histoire et la culture de Yamakasa, au service de la communauté locale. C'est un lieu où vous pourrez découvrir en toute quiétude l'énergie paisible qui se cache derrière l'agitation et son influence persistante sur votre quotidien.
Être sincère sous le regard de Dieu

À gauche : le superviseur Tsuyoshi Yamaguchi, au centre : l'officier des affaires générales Etsuro Imamura, à droite : l'officier des affaires générales Toshihiko Muraishi
Le Hakata Gion Yamakasa n'est pas un spectacle. C'est une cérémonie religieuse, et la question de savoir pourquoi elle a lieu est au cœur de l'attention de tous les participants. C'est pourquoi, derrière cette extravagance, se cache une présence calme et digne.
Muraishi déclare : « Les festivals ne sont pas seulement une question de divertissement. Je pense qu'il est important d'être honnête devant les dieux et d'aborder chaque chose avec sincérité afin de la prendre au sérieux. »
Muraishi-san a été porteur de serviettes rouges, responsable de la ville et responsable junior de longue date. Passé du travail acharné sur le terrain à la supervision de l'ensemble du festival, il explique que sa « vision du festival » a radicalement changé.
« Maintenant que j'ai la cinquantaine, je ressens un charme et une gratitude que je ne peux pas exprimer avec des mots. »
Il dit également que l’interaction avec une variété de personnes différentes a donné au festival un sens plus profond.
« Les gens que je côtoie sont différents chaque année. C'est ce qui rend ce festival si intéressant. Sans même m'en rendre compte, j'ai l'impression que mon univers s'élargit un peu plus chaque année. »
Portant des manteaux happi uniformes et portant le drapeau avec leurs enfants et petits-enfants, ils dégagent un sentiment de solidarité non pas basé sur les liens du sang mais au nom de la « ville ».

Les fêtes et les traditions locales sont transmises aux enfants

Les enfants marchent fièrement avec leurs pères sur la scène du défilé Oi Yamakasa
Enfin, il a déclaré : « Je souhaite me souvenir de l'histoire et des traditions tissées par mes prédécesseurs et continuer à maintenir une attitude digne. Je souhaite également aborder chaque événement avec gratitude, car je participe au deuxième Nakasu-nagare du Hakata Gion Yamakasa en 2025. »
Il ne s’agit peut-être pas seulement des techniques et des formes qui sont transmises, mais aussi de choses comme « l’atmosphère » ou « l’espace ».
Cette année encore, les chars Yamakasa parcourront les rues et leurs voix résonneront dans les airs.
En été à Hakata, une file de personnes debout devant les dieux crée une scène calme et puissante.
博多祇園山笠振興会
電話番号:092-291-2951
住所:福岡県福岡市博多区上川端町1-41 博多総鎮守 櫛田神社内
アクセス:ホテルリソルトリニティ博多より徒歩7分
HP::https://www.hakatayamakasa.com/
詳細は上記のリンク先でご確認ください。